
沖縄は、日本本土とは異なる独自の歴史と文化を持つ地域です。そのため、沖縄の考古学的な遺物や遺跡は、本土と比べて大きな違いがあります。特に、古墳時代(3世紀から7世紀)の文化が発展した本土と異なり、沖縄には古墳が存在しません。また、現在良く見られる沖縄のお墓は、本土の一般的なお墓に比べて非常に大きいです。これには、いくつかの理由があります。今回は沖縄のお墓事情について解説していきます!
1. 沖縄独自の墓文化。その歴史的背景は?
沖縄は、古代から本土とは異なる歴史を歩んできました。沖縄にいつ人類が住み始めたか、はっきりとはしていませんが、琉球諸島最古の人骨は那覇市で発見された山下洞人(3万2000年前のもの)で、それは旧石器時代になります。
沖縄諸島には、最初に人々が定住し始めたのは縄文時代からとされ、独自の文化が育まれました。沖縄の先住民である「琉球人」は、古墳時代に本土で見られたような大規模な墳墓を築く習慣を持っていなかったと考えられています。
一方で、沖縄には「グスク」と呼ばれる古代の城郭や遺跡が多数存在しています。グスクは、沖縄特有の社会構造や文化を反映したものとされ、後の琉球王国の発展にも深く関連しています。しかし、これらの遺跡は本土の古墳とは異なり、墳墓としての機能を持たないため、古墳の存在は確認されていません。

仁徳天皇陵古墳:前方後円墳
2.沖縄の墓文化に与えた地理的・文化的な影響
沖縄が本土と異なる文化圏に位置していることも、古墳の不在に影響を与えた要因の一つです。
古墳は、水稲農耕社会を基盤として造られたもので、北海道、東北北部、南西諸島を除いた日本列島全体に約16万基ほど造られました。共通の葬送儀礼様式・共通の墳墓様式に基づいて造られたということは、上から下へとルールや立場が決まっている仕組みがあるとわかります。この階層的な仕組みを成り立たせていた政治勢力をヤマト王権と呼び、古墳の形と規模は、被葬者の王権内における政治的身分を反映しています。そして身分の頂点に位置したのが全長200mを超す巨大な前方後円墳で、多くは当時の最高権力者である大王の古墳です。
これに対し、沖縄には古墳時代が存在していません。石器時代に続き貝塚時代が鎌倉時代の頃まで続きます。沖縄の墓地や葬儀の形式は、風葬という独自の慣習です。風葬とは、遺体を服を着せた状態で雨風にさらして風化させるという葬送のことです。亡くなった後は自然に還るという「ニライカナイ」という自然回帰の思想があり、また土地が狭く火葬設備があまりなかったことが、風葬が続いた理由です。
3. 沖縄に古墳文化が伝播しなかった理由
古墳文化は、朝鮮半島にも伝播したと考えられていますが、沖縄はその文化圏から離れており、古墳文化が広まることはありませんでした。本土との交流が始まった頃には、古墳時代が終わっていたことも理由の1つです。また、沖縄には他の地域とは異なる死者の扱い方や墓の形式が存在し、これが古墳文化の広がりを妨げたと考えられています。
沖縄の墓文化は、後の時代においても独自の発展を遂げ、特に「破風墓」「亀甲墓」など、特異な墓の形態が見られます。また、近世から戦後まで、遺体を土に埋めずに外気に晒す「風葬」をし、数年後に遺骨を「洗骨」してお墓に納骨する葬礼を行っていたとされます。

シルミチューの墓
4. 沖縄の墓の形態は?
沖縄の墓の特徴は、その大きさです。ちょっとした家と同じくらい大きいです。
墓が大きい理由は葬法が風葬であり、遺体を体を安置する場所、洗骨後にお骨を納める厨子を納める場所が必要とされたからです。厨子も他府県の骨壺に比べると大きく、スペースを必要とします。 また、複数の家族で使うため一定の大きさが必要だったことも沖縄のお墓が大きくなった理由のひとつです。
1500年代に入ると風葬の風習は、その周りを石積みするようになり、人工的に手を加えて掘りを大きくし、屋根を作るようになっていきました。そうやって作られるようになったのが「破風墓」と呼ばれる家型のお墓です。初期に登場したと思われるお墓は、第二尚氏で琉球国王のお墓である玉陵(たまうどぅん)です。こちらのお墓は、現在の一般的なお墓である「破風墓」のデザインをしています。破風墓は今でも沖縄県内で非常にポピュラーな形の一つですが、この玉陵にルーツを持っていることが分かります。そのほか、糸満市の「幸地腹門中墓」も「破風墓」のデザインをした有名なお墓です。

玉陵:破風墓
そして、もうひとつ、沖縄のお墓でポピュラーなデザインである、「亀甲墓」の登場は、1600年代以降であると考えられています。「亀甲墓」や「破風墓」のようなお墓を造るようになったのは16世紀以降のことで、長い琉球の歴史でいうと意外と最近のことです。沖縄の初期の亀甲墓は、伊江御殿墓(いえうどぅんばか)や護佐丸の墓などが有名です。

伊是名殿内の墓:亀甲墓
これらの古いお墓が岩壁を背にしている大きな墓であるのに対して、現在、個人墓の多くは平地に建てられた家形のこじんまりとした「破風墓」で、「ヤーグワーバカ」とも呼ばれます。
まとめ|沖縄の墓文化
沖縄に古墳が存在しない理由は、単に文化的な差異だけでなく、地理的、歴史的な要因が絡み合っています。沖縄は、本土とは異なる独自の文化を発展させ、墓の形態や葬儀の習慣も本土とは異なる進化を遂げました。このような背景から、沖縄には古墳のような大規模な墳墓が築かれませんでした。
沖縄の来た際には、沖縄独自の文化を感じられるお墓を訪れてみてはいかがでしょうか?特に玉陵は、第二尚氏の歴代国王の墓として歴史的な価値が高く、「琉球王国のグスク及び関連遺産群」として世界遺産に登録されているので、おすすめです!
当社では総合的に土地を評価して買取価格を提示させていただきております。一人一人に担当が付きますので初めてのご相談でも、安心してご利用いただけると思います。お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
まずは無料ネット土地査定からどうぞ~♪
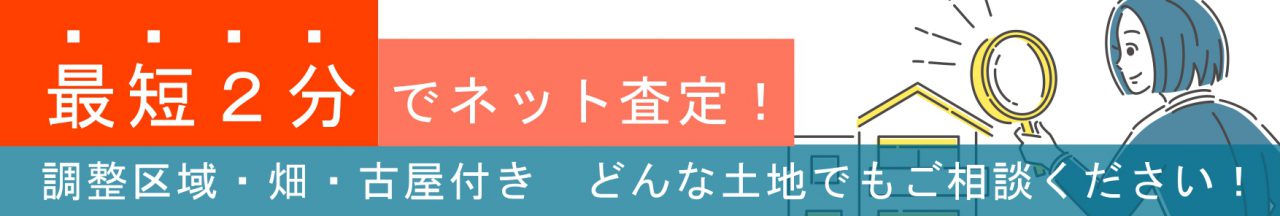 アイエー土地買取ナンバーワン宣言!
アイエー土地買取ナンバーワン宣言!
他社で買い取りを断られた土地を売りたい…
相続問題で早急に土地を現金化したい…
農業を引退して使わない農地を活用したい…
査定なら株式会社アイエー!高価買取中です!
おすすめコラムはこちら!
おすすめコラム:シロアリ対策をする前に生態を知るべし!不動産屋がオススメする対策とは
おすすめコラム:土地の価格の決め方を不動産が解説!一物五価って知っている?


